Rose Cottage
肉親と呼べる人間は、もう写真の中にしか残っていない。それはこの時代、この世界において珍しいことではなかった。むしろ、写真が残っているだけ幸運な方だと言えるだろう。母の笑顔も、優しい手も、やわらかな匂いも、すべてすべて土の中で分解されて天に還ったあと。母が残したものは多いとはいえないが、生前の母を知るファミリーのみんなが、ときおり寝物語として話してくれる出来事を、うっすらと残る記憶とつなぎ合わせて想像することで、私は自分の母の存在を実感できた。母の遺品は、今はもう私のものになったドレスとわずかな宝石、母の従兄妹からもらったという傘と、母が死ぬ少し前、母から譲り受けた鍵。あとは数冊の日記帳。その少ないアイテムに母の面影を探し、母の生を想像し、ファミリーのみんなが語る母の姿を夢想した。母の両親は母が幼い頃に他界しているし、年上の従兄妹は私が生まれる前に異国に渡っているらしく会ったことがなかった。その母の従兄は私が所属するファミリーを創設した人間であり、私がこのファミリーに在籍する以上は名を聞かぬ日はないと言っていい。屋敷にはその人の写真が飾られ、先代からの構成員は今のボスの野心的なさまを嘆くのにその人の名前を出した。そして私を引き取った男はことあるごとに、初代ボスであるボンゴレⅠ世、ジョットを憎々しげに語る。しかしその人との「繋がり」を、私が実感することは一度もなかった。血縁であるという事実は他人から与えられた情報のひとつでしかなく、その人は私にとって、先代のボスであるということ、それ以上の感情は微塵もなかった。
そして、母以外にもうひとり。私をこの世に存在させるに必要な、もう片方。
父に関して、私が持ち得る最初で最後の記憶は、ボンゴレ地下に設置されている死体安置所の中でのほんのわずかな邂逅、それだけだった。
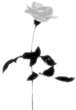
母が死んだとき、私はまだ五歳だった。
私を産んでから前線を離れていた母は、ボンゴレアジトから少し離れた静かな別荘で、私と数人の使用人とともに暮らしていた。尋ねる人間は少なく、魚屋やら肉屋やらが食料品を運んでくるか、母宛の小包みを運んでくる黒服の男くらい。今になってわかったことだが、その小包みの送り主こそが私の父、アラウディだった。
私の父は初代雲の守護者であり、ジョットがボスの座を譲り異国に渡ってからはCEDEFという外部組織を創りそのトップの座に収まった。諜報活動を主な仕事とする父とその部下たちは滅多にイタリアに帰らず、常に世界中を飛び回っていて、父が母のもとに顔を見せることはほとんどなかったという。それだけ聞けば、父は母のことなど愛してはいなかったのではないかと思われても仕方ないと思うし、私の両親について、夫婦仲は良好とは言えなかったと語るファミリーは多い。もちろんそれを私に直接言う人間はいなかったが、悪い噂というのはどうしてか耳に入れるべきでない人間にこそ集まってくるものである。元は某国の諜報組織のトップであったという父。母と結婚したのは、母が当時のボンゴレボス、ジョットの血縁であったからだとか、ジョットが父をボンゴレに引き入れるために母を捧げた、いわば政略結婚であったとか。
しかし私を引き取った男は、その噂のすべてを否定し、アラウディは私の母を唯一無二の存在として深く愛していたと断言した。そして私もその言葉は真実であると思っている。それはなにも、母を失ってから今までの私を世話してくれたその男を、盲信しているからではない。私は確信しているのだ。父は誰よりも深く母を愛していたと。少なくとも、母が死んだあの時。父は母を、母だけを愛していた。
母が死んだ時のことを、鮮明に覚えているわけではない。けれど、短い父との邂逅は、よくよく覚えている。
真っ白な部屋の真っ白なベッドに、真っ白なドレスを着せられ横たえられた冷たい母の死体。私をその部屋に連れてきたのが今の養父で、男は私を抱き上げて、母の顔を見せてくれた。まるで寝ているように綺麗で、穏やかな死に顔だった。けれどいくら揺すぶっても母が目を開けることはなく、微笑んでくれることも私の名前を呼んでくれることもなかった。ぬくもりもやわらかさもどこかへ消えていて、その欠けたものこそ母の命なのだと、幼い私は漠然と感じていた。
仕事があるからと男が私を残して安置所を出て行ってからしばらくの間、ぼんやりと母の手を握っていた。薄布一枚隔たてような現実感のなさ。冷たくてかたい母の手。私以外に誰も生者のいない部屋。静かな静かな、部屋の中。そこに、音もなく入ってきた、黒い影。私と同じ色の瞳を持つ、美しい男。
白黒の写真でしか見たことのなかった、私の父だった。
父は私に見向きもしなかった。真っ直ぐにベッドに近づいて、母だけを見つめた。手袋を外して母に触れ、髪を撫でて、ゆっくりとキスをして、小さく母の名前を呼んだ。
「」
私が父の声を聞いたのはそれっきり。母の名を、掠れる声で囁いた、それきり。
父はもう一度キスをして、のろのろと顔を上げて。ぼんやりと部屋を見回してから、ようやく私の存在に気付いた。それまで母にしか意識を向けていなかった父が、初めて私を視界に入れた。けれど私を見たようで、おそらく父は私を見つめていなかったのだろう。父の青い瞳は私の姿こそ目に映したが、あの青は私のことなんて眼中になかった。父の微かに動いた唇は何を紡ごうとしたのか、私にはわからない。それはきっと、私に向けての言葉ではなかった。
私が見上げる前で、父の白い肌をするすると一筋の涙が流れていく。私と同じ青い瞳が、星のようにきらめいた。瞬きとともに、母や私のそれよりも、白に近い金の睫毛が涙で光る。私とは違う色。父の髪は美しい白金だった。
例え母に写真を見せられていなくとも、私はこの人が自分の父親だと気付いただろう。私と違う髪。母と違う静かな空気、冴え冴えとした佇まい。そして、私と同じ、青い瞳。
目を合わせた瞬間に、理屈ではないどこかで父との血の繋がりを強く感じた。そして、父の流した涙、瞳に浮かんだ感情、微かに空気を震わせた囁きに、母への絶えようのない想いを見た。父は母を愛していた。滅多に国に戻らず、別荘に顔を出すこともなかったけれど。父は母を愛していた。誰よりも。
私はその事実を、30分にも満たない邂逅で理解した。
それから父は姿を消した。任務でボンゴレを離れていたそれまでとは違う。CEDEFの部下たちに目的や行き先を告げることもなく、父は忽然と行方を眩ませた。長い間。普通であれば裏切り者として追われてもおかしくないが、事情が事情であることや初代ボスへの貢献などから父の失踪は保留扱いとなり、表向きは「アラウディは特別任務に出た」ということになった。事実上、門外顧問の座は空席になる。もともと自由人のような父であったらしいが、それでもひとつの組織を預かる身であり、それも諜報組織だ。アラウディが握っていた様々な情報は散逸し、進めていた多くの計画が振り出しに戻ったり潜入捜査が打ち切りになったりと、当時のCEDEFは大混乱だったらしいが、それも数十年以上も前のことである。今となっては「あの頃は辛かった」などと酒の肴にされるような、そんなエピソードだ。
アラウディが消えた理由についてファミリーの人間やボンゴレの研究家を自称する者たちがあれこれ推測しているが、どれも的外れだと私は思う。
政略結婚からの解放、母を殺した犯人探し、エトセトラエトセトラ。母のあとを追って自殺したのでは、などと言っている人間もいるらしい。けれど、私はどれも違うと断言できる。父の何を知っているかと問われれば、何も答えることはできないけれど。それでも、私はすべてを確信を持って否定する。
父が消えた理由はただひとつ。父は母を愛していた、誰よりも何よりも深く愛していた。それゆえに父は耐えられなかったのだ。母の喪失に。母が消えたイタリア、母が消えたボンゴレに、父は耐えられなかった。
最強の守護者と謳われた父。一人を好み、孤高の浮き雲と称された父の姿からは、きっと誰も想像することはできないだろうけれど。私にはわかる。父が消えた理由も、私を残して去った理由も。そしておそらく、父の行き先も。
目を合わせた瞬間に、私が父を父だと理解したと同じように、きっと父も、私が誰であるか理解しただろう。理屈ではない、どこかで。自分の妻の手を握る小さな子供が誰であるか。己と同じ瞳を持ち、妻と同じ髪を持つ幼い娘が、誰であるか。
確かに父は強い人だったのだろう。強く気高い男だったのだろう。ファミリーが語る初代・雲の守護者はそういう人間だったのだろう。しかし父は、アラウディというひとりの男は、強いだけの人間ではなかったはずだ。冷たい白い部屋の中、母だった器をぼんやりと見つめて涙を流した男は、耐え切れぬほどの喪失を埋めるために動ける人間ではない。父の喪失を埋めることができるのは母だけで、母に似た私でもその代わりにはなれない。永遠に埋まらない喪失は、誰も知らない遠い土地で、ゆっくりと、静かに、薄めていくしかないのだ。長い長い時の中で。
父は忘却を望まないだろう。きっといつまでも、母を、母への愛を、握りしめ続けるだろう。母の存在、死したことも含めたすべてが、握りしめた肌から、父の中にとけてゆくまで。そうして父の中に、母のすべて、とけきったとき。ようやく父は、動き出すだろう。そのあと何をするのかは、娘の私にもわからない。
ただ、動き出した父が、一瞬でもいい。私の存在を、思い出してくれたら。私と会うことを望んでくれたら。
もし再び父に会えたその時は、父の中にとけきった母のすべてを、私に教えて欲しい。父が見た母のすべて。父が愛した、母のすべて。私の中に、とけてゆくまで。
- Back -
